経済を「人の暮らし」として見つめ続けてきた学者、若田部昌澄さん。
早稲田大学で教鞭をとり、日本銀行の副総裁として金融政策にも携わってきました。
理論と現実、学問と社会――その両方を見据える姿勢が、多くの人の注目を集めています。
今回の記事では、彼の専門性や歩みを丁寧に追いながら、「数字の裏にある人の営み」を見つめる姿勢の本質に迫ります。
基本プロフィール
名前:若田部 昌澄(わかたべ まさずみ)
生年月日:1965年2月26日(神奈川県生まれ)
出身校:
早稲田大学 政治経済学部 経済学科 卒業
早稲田大学大学院 経済学研究科 修了
トロント大学 経済学大学院 修士課程 修了
主な職歴:
早稲田大学 政治経済学術院 教授
日本銀行 副総裁(2018年3月〜2023年3月)
ケンブリッジ大学・コロンビア大学・ジョージ・メイソン大学 客員研究員
専門分野:
経済学史
中央銀行論
金融政策論
受賞歴:
『昭和恐慌の研究』(共著)で日経・経済図書文化賞受賞(2004年)
『危機の経済学』で石橋湛山賞受賞(2010年)
人物の特徴:
理論と現実の両方に軸足を置く実践派の経済学者
学問の原点に「人の暮らしを支える経済」という哲学を持つ
教育者としても人気が高く、学生から“穏やかで誠実な教授”として慕われている
生い立ちと幼少期
神奈川県で生まれ育った若田部昌澄さんは、幼いころから身の回りの「しくみ」に強い関心を持つ子どもでした。
「なぜ物の値段は変わるのか」「どうして景気がよくなったり悪くなったりするのか」――そんな疑問を抱きながら、毎日のように新聞の経済欄を覗き込んでいたといいます。
周囲の同級生が漫画やスポーツに夢中になる中、若田部少年の興味は“社会の動き”や“数字の裏にある人の行動”に向いていました。
数字を追うだけでなく、歴史を読み解くことも好きだったため、理系の論理と文系の洞察、その両方を併せ持つバランス感覚が自然と育っていきます。
高校時代には、経済や政治に関するニュースを自分なりに要約してノートにまとめる癖もあり、既に「社会を理解したい」という知的な探究心が芽生えていました。
この“観察する目”と“考え続ける姿勢”こそが、のちに彼を経済学者の道へと導く最初の原動力になったのです。
活動の転機・挑戦
大学・大学院で経済学を徹底的に学んだ若田部昌澄さんは、卒業後、自然な流れのように研究者としての道を歩み始めました。
早稲田大学で教鞭をとりながら、学生たちに「経済は人の暮らしそのものだ」と語りかけ、机上の理論を“現実に息づく学問”として伝え続けました。
その一方で、若田部さんの探究心は国内にとどまりません。
ケンブリッジ大学、ジョージ・メイソン大学、コロンビア大学といった海外の研究機関に客員研究員として滞在し、世界の経済学者たちと意見を交わしながら、日本経済の課題を国際的な視野で見つめ直しました。
理論だけでなく、「どうすれば社会をより良くできるか」という実践的な問いを常に胸に抱いていたのです。
そして2018年、ついに転機が訪れます。
日本銀行の副総裁に就任し、研究室で培った理論を“政策の現場”に持ち込みました。
学者として積み上げてきた知見を、今度は国の金融政策に生かすという挑戦――それは、静かな研究者だった彼が初めて「日本経済という大舞台」に立った瞬間でもありました。
理論を現実に結びつけるという使命。その姿は、経済を「生きた学問」として捉える若田部さんらしい挑戦だったといえるでしょう。
苦悩と生き方
日本銀行の副総裁として迎えた5年間、若田部昌澄さんはまさに“経済の嵐”の中心に立っていました。
デフレからの脱却が見えそうで見えない――そんな長いトンネルの中で、円安やインフレ、さらにはマイナス金利という前例のない難題に次々と直面します。
経済学者として積み上げてきた理論をもってしても、現実の経済は一筋縄ではいかない。
「数字が正しくても、人々の生活が苦しいなら、その政策は成功とは言えない」――若田部さんはそう語り、政策を“暮らしの視点”から見つめ直しました。
会見では声を荒らげることなく、いつも穏やかな語り口で、しかし一言ひとことに重みを込めて説明する姿が印象的でした。
そこには「理論のための経済ではなく、人のための経済を」という静かな信念が貫かれていたのです。
数字の先にある現実を見つめる。
学者でも官僚でもなく、“人間としての判断”を大切にする姿勢こそ、彼が副総裁として残した最も大きな足跡でした。
恋愛・結婚・人間関係
現在、若田部さんの公開された恋愛・結婚関係の情報は、信頼できる情報源では確認できておりません。公の場では、教育・研究・政策という分野での人間関係に重きを置いて活動されている姿が印象的です。
最近の活動・最新ニュース
2025年11月6日、政府が若田部昌澄さんを経済財政諮問会議の民間議員に起用する方向で調整しているという報道が流れました。
日銀副総裁として金融政策の最前線に立ってきた彼が、今度は国の経済運営全体を見渡す立場に回る――それは、再び“理論と実践の橋渡し役”を担うことを意味しています。
若田部さんは、長年にわたり「リフレ派」として知られています。デフレ脱却には積極的な金融緩和が必要だと唱え、経済成長の土台を“お金の流れ”から整えることを重視してきました。
一方で、政府が掲げる「責任ある積極財政」は、財政出動による景気刺激を重視する政策。両者は似て非なるアプローチであり、どのようにバランスを取るのかが今後の焦点です。
金融と財政――この二つの舵をどう連動させ、日本経済を安定させるのか。
その舵取りに、若田部さんがどのような提言を行うのかに多くの注目が集まっています。
理論家でありながら現実主義者でもある彼が、再び日本の経済政策にどんな風を吹かせるのか――静かな期待が高まりつつあります。
実績
- 著書『昭和恐慌の研究』(2004年)で日経・経済図書文化賞受賞。
- 著書『危機の経済政策』で石橋湛山賞受賞。
- 日本銀行副総裁として量的・質的金融緩和政策を支える理論的支柱を務め、経済政策の現場に影響を与えました。
- 教壇に戻ってからも、若手研究者・学生育成に力を入れ、教室と政策現場をつなぐ橋渡しの役割を果たしています。
まとめ
理論と現実、教える場と政策の場、静けさと情熱——。そのどちらもを大切にしてきたのが若田部昌澄さんです。
数字の向こうに「人」を見つめ続け、日本経済の重荷を支える理論を生み出してきた彼。
派手さはないかもしれませんが、誠実に積み重ねたその歩みが、多くの人の信頼を集めています。
「学びとは、正しさを身につけることではなく、考えながら進むこと」——この言葉が、彼の人生を表しているように思います。
FAQ(よくある質問)
Q:若田部昌澄氏は結婚していますか?
→ 公に確認できる結婚・配偶者の情報は確認されていません。
Q:なぜ若田部氏が副総裁に選ばれたのですか?
→ 経済学史・中央銀行論を専門にし、量的・質的金融緩和政策を理論的に支えてきた実績が評価されたとされています。
Q:今後の活動予定は?
→ 現在、経済財政諮問会議の民間議員起用が調整中であり、今後の政策議論において重要な役割を担う可能性があります。
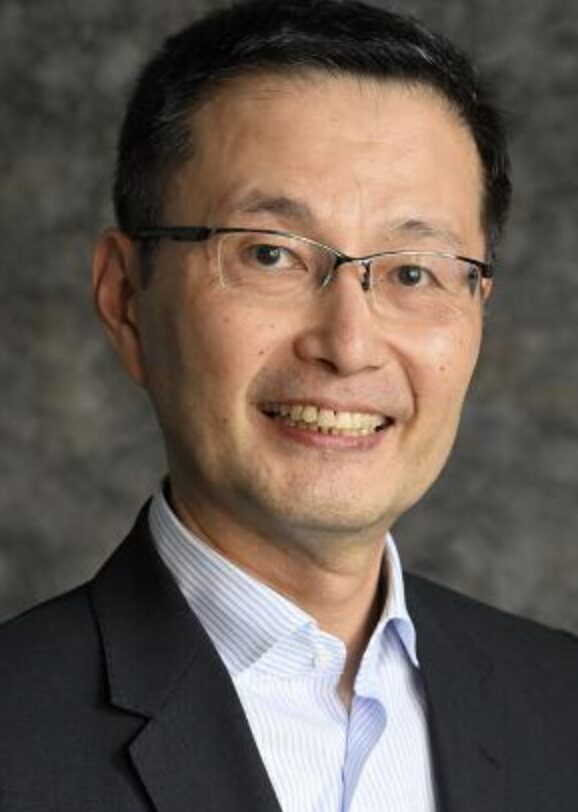


コメント