今回は、「がんを寄せ付けない」と世界中の研究で明らかになった9つの優良食材をご紹介します。中にはダイエット効果が期待できる食材もあるので、健康的に体を整えたい方にも必見の内容です!
Contents
■ がんが逃げていく食べ物とは?共通点を知ろう
「がんが逃げていく食べ物」に共通する作用について、それぞれのメカニズムや関連研究を交えて詳しく解説いたします。
✅ 1. 強い抗酸化作用(フリーラジカルの抑制)
私たちの体内では、呼吸やストレス、紫外線、喫煙などにより「活性酸素(フリーラジカル)」が日々発生しています。
この活性酸素は細胞のDNAを傷つけ、がんの原因となる突然変異を引き起こす**ことがあります。
食材に含まれる抗酸化物質(例:リコピン、ビタミンC、ポリフェノール、セレンなど)は、
このフリーラジカルを無害化し、細胞を酸化ストレスから守る働きを持っています。
- アメリカ国立がん研究所(NCI)は、抗酸化物質の豊富な食事を摂ることでがんの予防効果があると発表。
- 国立健康・栄養研究所でも、抗酸化成分がDNAの損傷リスクを低減することが確認されています。
✅ 2. 抗炎症作用(慢性炎症の抑制)
慢性炎症は「がんの温床」と言われ、組織の炎症が長期間続くことで細胞ががん化しやすくなることがわかっています。
これは、腸炎からの大腸がん、肝炎からの肝がんなどが代表例です。
ブロッコリーのスルフォラファンや、ターメリックのクルクミン、魚のオメガ3脂肪酸などは、炎症性サイトカインの産生を抑える作用があるとされ、体内の炎症を沈静化します。
- British Journal of Cancerにて、慢性炎症とがんの直接的な因果関係を明示。
- クルクミンやオメガ3脂肪酸がNF-κB(炎症の指令物質)を阻害することが複数の実験で確認。
✅ 3. 発がん物質の無毒化・排出促進

私たちの体は日々、食品添加物、農薬、タバコの煙、排気ガスなどに含まれる発がん物質にさらされています。
しかし、特定の栄養素には、これらの物質を分解・無毒化して体外へ排出する働きがあります。
特にブロッコリーやキャベツに含まれるイソチオシアネート類や、にんにくのアリル化合物は、肝臓の解毒酵素群(フェーズ2酵素)を活性化させ、がんの引き金になる有害物質の代謝・排出を助けます。
- ジョンズ・ホプキンズ大学の研究で、スルフォラファンの摂取により発がん性物質の体外排出が促進されたと報告。
- 世界がん研究基金(WCRF)も、アブラナ科野菜に強いがん予防作用があると推奨。
✅ 4. がん細胞の増殖を抑制し、自然死(アポトーシス)を促す
健康な細胞は一定の寿命で死を迎える「アポトーシス(自然死)」の仕組みを持ちますが、がん細胞はこの仕組みを回避して無限に増殖し続けます。
クルクミン、リコピン、セレン、ベリー類のエラグ酸などには、がん細胞に対してアポトーシスを促す働きや、細胞周期を止める作用が報告されており、がん細胞の進行・転移を食い止める上で重要です。
- カリフォルニア大学の研究では、リコピン摂取によって前立腺がん細胞の増殖抑制が確認。
- オハイオ州立大学の実験にて、ブラックラズベリーががん細胞の成長を選択的に抑制する働きを持つと発表。
がんは一朝一夕では防げませんが、日々の積み重ねがそのリスクを大きく下げることは多くの研究が証明しています。
抗酸化・抗炎症・解毒・増殖抑制という4つの防衛力を備えた食品を継続して摂ることで、体は自らがんに立ち向かう力を育むのです。
それでは、具体的な食材を見ていきましょう。
1. 全粒穀物(オーツ麦、玄米、全粒粉パンなど)

主な成分:食物繊維、ビタミンB群、抗酸化物質(フィチン酸など)
科学的根拠:ハーバード公衆衛生大学院の研究では、全粒穀物の摂取が乳がんのリスクを低下させると報告されています。これは、食物繊維が腸内環境を整え、エストロゲンの代謝を助けるためです。
また、全粒穀物に含まれる抗酸化物質は細胞の酸化ストレスを抑制し、発がんリスクを下げることがわかっています。
2. トマト(加熱調理が特におすすめ)

主な成分:リコピン、ビタミンC、ベータカロテン
科学的根拠:リコピンには非常に強い抗酸化作用があり、前立腺がんや乳がん、胃がんの予防に有効とされます。
特に、リコピンは加熱することで体内吸収率が3〜4倍に上がるため、トマトソースやスープがおすすめです。
3. ブロッコリー(アブラナ科野菜)
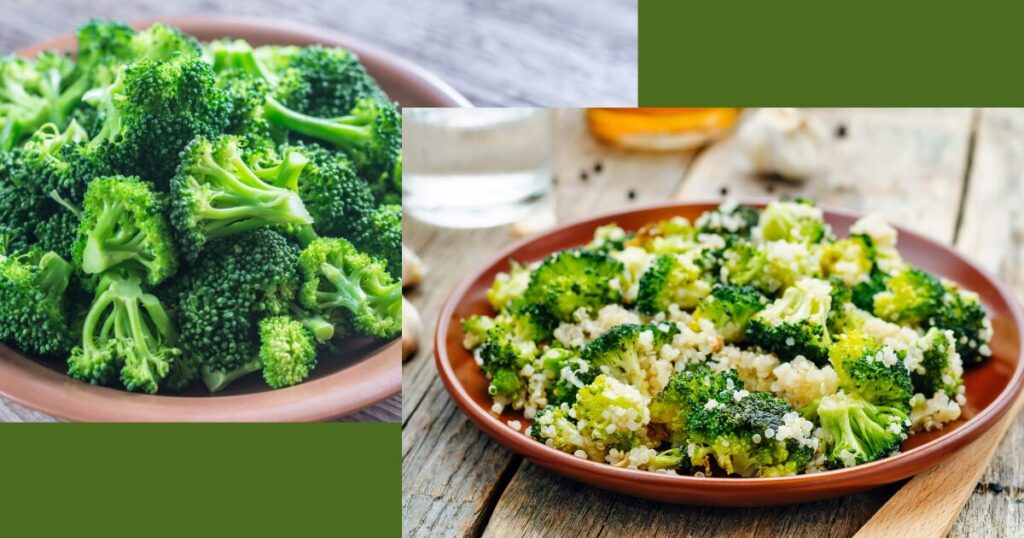
主な成分:スルフォラファン、イソチオシアネート
科学的根拠:ジョンズ・ホプキンズ大学による研究で、スルフォラファンががん細胞の増殖を抑え、前立腺がんや胃がん、乳がんの発症リスクを低下させるとされています。
さらにブロッコリーとトマトを一緒に摂ることで、相乗的ながん予防効果が得られるという報告も。
4. ブラックラズベリー(ベリー類)

主な成分:エラグ酸、アントシアニン、ビタミンC
科学的根拠:オハイオ州立大学の研究では、ブラックラズベリーが口腔がんの進行を遅らせる作用を示したと発表されました。
また、エラグ酸にはDNAを保護し、がん細胞のアポトーシス(自然死)を促す効果も確認されています。
5. ニンニク(アリウム属の野菜)

主な成分:アリシン、二硫化アリル
科学的根拠:シドニー大学による2万人超の調査では、ニンニクを多く摂取する人ほど胃がんリスクが低いという結果が得られています。
また、アリシンはがん細胞の代謝を阻害し、細胞死を誘導するというメカニズムも解明されつつあります。
6. 鮭・青魚(脂の多い魚全般)

主な成分:EPA、DHA(オメガ3脂肪酸)
科学的根拠:International Journal of Cancerに掲載された論文によると、脂の多い魚を週1回以上食べる男性は、前立腺がんのリスクが57%低下。
また、カンザス大学の研究では、乳がん予防にも有効であることが示唆されています。
7. ターメリック(うこん)

主な成分:クルクミン
科学的根拠:クルクミンはがん細胞の増殖抑制、転移防止、アポトーシス誘導に有効とされ、大腸がん、肝臓がん、膵臓がんなどへの予防効果が期待されています。
インドでは、がん発症率が低い背景の一つに「日常的なターメリックの摂取」があるとする見解も。
8. キノコ類(しいたけ、しめじ、まいたけなど)

主な成分:βグルカン、エルゴチオネイン
科学的根拠:「International Journal of Cancer」によると、毎日2カップ(約150g)のキノコを食べると、乳がんリスクを3分の2まで減らせるとの研究結果があります。
βグルカンは免疫力を活性化し、がん細胞を攻撃するナチュラルキラー細胞の働きを高める作用も。
9. ブラジルナッツ

主な成分:セレン(セレニウム)
科学的根拠:セレンは強力な抗酸化ミネラルで、DNAの修復やがん細胞の増殖抑制に役立つことがわかっています。
ただし、1日1〜2粒程度が適量で、過剰摂取は毒性のリスクがあるため注意が必要です。
【補足】リンゴとにんじんジュースの力も侮れない

リンゴに含まれる「ケルセチン」には、DNAを保護し、がんの発生を抑える働きがあるとされ、欧米ではがん治療中の補助食品としても活用されています。
特に「リンゴ+にんじんジュース」はがん食事療法の定番メニューとして浸透しつつあります。
■ まとめ:毎日の食生活が未来の健康をつくる
がんは誰にとっても他人事ではありません。しかし、毎日の食事を少し意識するだけで、そのリスクを大きく減らすことができます。今回紹介した9つの食材を少しずつでも取り入れることで、がん予防+ダイエット+アンチエイジングと、一石三鳥の効果が期待できます。
無理なく、でも意識的に。
今日から「がんが逃げていく食べ物」を、あなたの食卓に。
【参考・引用元】
- Harvard T.H. Chan School of Public Health
- Johns Hopkins Medicine
- International Journal of Cancer
- Ohio State University Cancer Research
- シドニー大学 医学部
- カンザス大学医療センター
- 精神科医 樺沢紫苑『樺チャンネル』
#抗炎症食 #慢性炎症 #がん予防生活 #青魚の力 #スルフォラファン #クルクミン効果 #食べる予防医学抗酸化作用 #リコピン #ビタミンC #フリーラジカル対策 #がん対策 #食事で予防 #ナチュラルケア #美容と健康


コメント